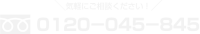ピアノの音が漏れてあちらこちらに迷惑をかけていないか心配・・・
そんなあなたにピアノ調律師が厳選したピアノ防音対策方法をご紹介します。
ピアノの防音対策製品は色々な物が販売されていますが、それぞれ一長一短があり、
どれが自宅にベストマッチングするのか判断するのが難しいです。
例えばネットで検索すると価格もピンキリで、数千円から数十万円と
その幅は余りにも大きくて、どれがどの位の効果が有るのかも分かりづらいです。
そこで日頃からピアノの調律でご自宅にお伺いしているプロの調律師が、
これまでの経験と知識からあなたのお宅にベストな防音対策方法をご紹介します。
このページを読んで防音対策をすれば、
後でもっとしっかりした対策をしておけばよかったとか、
もっと簡単な方法で防音が出来たのに、なんて後悔をしないで済みます。
この記事についてのお問い合わせはこちらからどうぞ℡ 0120-045-845
またはbzq21747@gmail.comにメールで問い合わせてください。
ピアノ職人・VIRA JAPAN
(有)ラッキーパイン
〒243-0804 神奈川県厚木市関口466‐1
1.計測器で防音効果は測れない
防音対策について説明する前に注意して欲しいことは、
計測器の数値的に騒音基準を下回っているといっても、
必ずしもそれで防音になっていないことです。
その理由として、以下の2つが挙げられます。
- ピアノの防音対策は 2 種類の音を抑える必要がある
- 音の大きさと不快感は比例しない
まずはこの 2 つについて、くわしく説明します。

1.ピアノの防音は2種類
ピアノの場合、音は空気を伝わって行く空気伝搬と
ピアノの脚などから床や壁を伝って行く個体伝搬の二つが有ります。
空気伝搬とは、読んで字のごとく音が空気を伝わって広がって行く事です。
ピアノは響板で音を増幅して音を出す仕組みですので、
ピアノを弾けば音が鳴ると言う当たり前の事が空気伝搬です。
多くの方はピアノの防音というと、この空気伝搬のことだけを考えがちですが、
もう 1つの個体伝搬のことも考える必要があります。
個体伝搬とは、ピアノの脚から音が抜けて、
床や建物のパイプ、鉄筋などを伝わって行く事を言います。
ピアノのような重量のある楽器は、脚から床に音が抜けて、
四方八方に広がって行く性質が有ります。
つまりピアノの防音と言ってもこの両方を抑え込まなければ防音対策にはなりません。
いくら窓を二重サッシにしても、ピアノの脚から建物自体に振動が伝わって
壁や床を鳴らすということが有ります。
このことから、防音を考えるときに空気伝搬と個体伝搬の両方とも対策する必要があります。

2.音の大きさと不快感は比例しない
又防音対策は、ピアノから発生する音を単純に小さくすればよいというものではありません。
何故なら音は不思議な性質があって、自分の好む音はうるさく聞こえないのに、
好まない音は、小さな音でも騒音に聞こえてしまうのです。
例えば水道の蛇口からポタッ、ポタッとしずくが落ちる音が気になって眠れなかったり、
時計の秒針のカチッ、カチッという音がうるさく感じる事があったりします。
これらの音は計測器で測っても静寂と言われる
40㏈(デシベル)前後の数値しか表示されません。 (※dB(デシベル)は騒音対策を測定する基準として使われる単位です。)
これと同じように、ピアノの防音対策をして外部で聞こえる音は小さくなったとしても、
漏れ伝わる音を騒音ととらえられてしまう可能性が有るのです。
このようにピアノから発生する音の大きさと周囲の与える不快感は比例しないことから、
数字だけで防音効果を測ることは出来ません。

さらに、ピアノと一口で言っても、グランドピアノもあればアップライトピアノも有ります。
置き場所も一戸建ての1階の場合とマンションの 10 階の場合では、
その防音対策も手法も全く違って来ます。
一日中生徒さんにピアノを教えているピアノの先生のお宅と、
小さなお子さんが一日一時間位ピアノを弾くくらいのお宅を比べたならば、
ピアノの先生のお宅に全く防音対策が無ければ、近隣の方からクレームが来るでしょう。
しかし子供さんがちょっと練習する位のお宅であれば、近所に声をかけて見たり、
練習の時間帯を気を付けるなどで防音対策は最小限で済むかもしれません。
つまり、ピアノの防音対策はピアノの種類、
ピアノを弾く延べ時間や住まいの形状、隣近所とのお付き合い度合い、
楽曲の種類、演奏者のタッチの強さなど、色々な条件がからんできます。
つまり、あなたが弾くピアノの種類と場所によって、音の伝わり方は全く違うのです。
その為に防音対策の方法も変わり費用も変わります。
2.防音対策で重要な3つのポイント
防音対策は
1.防音効果
2.音色変化
3.コスト
の3つが重要なポイントとなります。
この 3 つのポイントをおさえて防音対策を考えて行く事がとても大切です。
どの位の費用をかけてどの位の防音効果を期待するのかがポイントになります。
また、防音対策をすることでピアノそのものの個性を殺すことにもなります。
ピアノは演奏者の思い通りに音が鳴るように作られていますが、
防音効果だけを意識するとピアノの音が大きく変わってしまうこともあります。
その音色変化をなるべく小さく抑えながら、
外部に漏れる音を少なくすることが防音対策のポイントと言えるでしょう。
1.防音効果
防音と言っても外にもれる音が少し小さくなれば良いという簡易防音から、
外部には全く音がもれないようにする完全防音まで、
その幅は大きく、かかる費用も全くちがいます。
防音対策を音源に近い所で行えば、コストは抑えられますが
ピアノそのものの音色の変化も大きくなります。
逆にお部屋全体を防音工事して防音対策をやれば、かかる費用は大きくなりますが、
ピアノそのものの音色変化は少なくなります。
2.音色変化
もう一つ注意しなければならないのは、防音対策を行う事によって、
ピアノの音色が変わると言う事です。
そもそもピアノという楽器は、音が出るように作られている訳ですから、
その音を何らかの方法で外部に漏れないようにする、
または小さな音にするのが防音という事になります。
それはピアノを奏でる時の音のエネルギーを遮断するか、
または音のエネルギー自体を下げる事になります。
例えば、お風呂場で歌を歌うと上手くなったように感じる事があると思いますが、
これは風呂場では音が大きく反響する為、
自然なリバーブ効果(残響効果)がかかるからです。
ピアノも同じで、部屋の反響音によって演奏がカバーされて
上手く弾けるように感じることがあります。
しかし防音対策を考えた防音室等の閉鎖空間では、
防音効果を高めるために音の反射をおさえるような構造になっています。
その為、ピアノの音も反射を抑えられて防音室を作ったら
ピアノの音が響かなくなったりします。
ピアノを思いっきり演奏したいと思って作った防音室に入ったら、
音が死んだ音になってしまい、ピアノを弾くと気持ち悪くなるなんて事も有るのです。
ですから防音室を作る場合は、必ず事前にショールーム等で音がどの様な響きになるのかを確認することが必要です。
3.コスト
ピアノから発せられた音をどこで止めるかによってコストが変わります。
ピアノから発せられた音を、音源に近い所で防音対策を施したほうがコストは安くなります。
そして音源から離れれば離れるほど防音対策のコストは二次関数的に上がっていきます。
何故ならピアノから発せられた音を、音源に近い所で防音対策を施したほうが
コストが安くなるからです。
音源に近い・遠いでコストが大きく変わるため、ここからはそれぞれに説明します。
ピアノ近くでの防音対策コスト
最もコスト的に効率よく防音する方法は音源から音を出さないという方法です。
ピアノの音を空気中に拡散していくための、響板を振動させないという事になります。
この主な方法とコストは、以下のとおりです。
- 床に抜ける音を防ぐための防音インシュレーター・・・約 2 万円
- 床に敷く防音用マット・・・約 8 万 5 千円(六畳位の広さ)
- 窓の防音対策である防音カーテン・・・約 2 万円~8万円
ピアノの遠くでの防音対策
ピアノから離れたところでの防音対策のコストは
ピアノからの距離によって二次関数的に大きく上がって行きます。
具体的に言うと、防音室の大きさが大きくなるほどコストは高くなります。
防音室の費用は概算で、以下のようになります。
- 六畳位のユニット式防音室・・・150万円~200万円見当
- 六畳位の部屋全体の防音工事・・・300万円以上
なお、完全防音をめざすのであれば、さらにコストは上がります。
ケチって中途半端にお金をかけても結局は音漏れして効果に不満が残ったりします。

3.ピアノの5つの防音方法
ピアノ本体の音を小さくする、消す
ピアノそのものの音を消したり、音を小さくする方法での防音対策で、
一番コストパフォーマンスの良い対策となります。
何度もお伝えしている通り、音を音源に近い所で止める方法がコストがかからない方法
となりますが、反面音色の変化が大きくなる傾向が有ります。
その音色の変化をなるべく防いで、
音を思い切り出したい時には出せるような仕組みの防音対策としてお勧めなのが
アップライトピアノの場合にはサイレントユニットを取り付けるという方法です。
サイレントユニットのメリットは、
音を出したくないときはピアノの音を止めてヘッドフォーンで音を聞きながら演奏し
音を出しても問題ない時はサイレント機能を解除してピアノの音が出せる事です。
ピアノ本体からの音を出さない、もしくは極限的に小さくする事で、
建物自体には手を加えないのでコスト的に最有力候補です。
また、音の反響についてもヘッドフォーンで聞いたりピアノ本来の音が小さくなるため、
違和感は少なくて済みます。
ピアノから発する音量、音圧を下げる
「1.ピアノ本体の音を小さくする、消す」方法と違い、ピアノはそのままで、出てくる音を吸音して音量を下げる方法です。
この方法はピアノにも建物にも手を加えることなく、ある程度の防音対策が出来ますが、音色の変化を考えて設置した場合、防音対策品をピアノ本体からやや離して設置したりすることになり、防音効果が落ちる傾向が有ります。
この方法ですとある程度の防音効果は期待出来ますが、建物の構造や周りのお宅との位置などによって必ずしも外部への音を遮断出来るわけでは有りません。
ただ、最低限のエチケットとしての防音対策として考えたほうが良いでしょう。
方法としてはピアノの響板部分に音量を吸収する防音パネルを設置するのが一般的ですが、ピアノ自体を密閉してしまうと音が鼻づまりを起こしたような音になってしまいます。
その為防音効果は下がりますが、防音パネルをピアノから少し離した所に設置したりします。
ピアノから出る個体振動を抑える
ピアノの防音は音として認識出来るものに対しての対策にかたよりがちですが、実際には脚から抜ける音も大きいです。
従って防音対策は部屋全体に対して対策を施さなければ音漏れは解消しません。
特にマンションなどでは子供が駆ける足音が階下の部屋で騒音となって問題になることが有ります。
音は空気を振るわせて広がって行くのと同じ位、脚から抜けて建物全体を鳴らす事を忘れてはなりません。
特にマンションの構造によっては、鉄骨や排水用パイプ等を通じて音が伝わって行ってしまいます。
脚から伝わる振動エネルギーは以外に大きく、直下のお宅ばかりでなく、2階下や3階下のお宅まで届いてしまう事が有りますので、脚の防音対策は必須条件となります。
対策方法としては防音インシュレーターや防音マットを敷く方法で、
防音インシュレーターが約2万円、防音マットで約5万5千円から各種有ります。
ピアノから出る空気振動を抑える
ピアノから出る空気振動とは、つまり音の事です。
当たり前の様に思われるかも知れませんが、空気を振動させなければ音は聞こえません。
その振動エネルギーを抑えれば、音のエネルギーは小さくなり、聞こえにくくなります。
また、音の進む方向に誰もいなければ騒音とはなりません。
面倒くさそうな話しですが、理屈は簡単でお部屋のどの位置にどちらを向けてピアノを置くかという事になります。
その上で、音が向かって欲しくない方向に防音処理を施すという事です。
また、先に述べました「2.ピアノから発する音量、音圧を下げる」と同じと思われるかも知れませんが、ピアノ本体に蓋をして音を下げた場合、聞こえてくる音がどうしてもつまったような音になってしまいます。
その為に少し空間を作って音に柵を儲けてその空間内は自由に音が伝わるようにした方法だと考えて下さい。

高速道路の防音壁がまさにその方法で騒音を軽減しています。
つまり左右方向へ向かう音は湾曲した壁を作って道路側に反射させ、尚且つ塀の上部には位相を反転させる仕組みを作って騒音そのものを小さくするようにしています。
そして天井の上は空で人はいませんから、音を空の方向に誘導して上空に流すようにしています。
ピアノの場合は、音の出る響板部分(アップライトピアノの場合は背中、グランドピアノの場合は上下)方向の音を吸音したり、抑え込むことである程度防音効果が有ります。

お部屋の中でピアノを置く場所はどうしても限られてきますが、外部に向けてピアノを設置すよりは、部屋の中方向に向かってピアノを設置したほうが外部への音漏れは軽減します。
加えて吸音材と遮音材を使った遮蔽版を設置することで、空気伝搬を抑える事が出来ます。
部屋全体を防音する。
これまでお伝えしてきた方法では防音対策が不十分と言う場合は、お部屋全体の防音工事が必要となります。
つまり完全防音にしないと防音対策にならないという事です。
これまでお伝えしてきた方法は簡易防音で、音を止めるのでは無く、漏れる音を少なくする為の方法だったからです。
例えば、ピアノのレッスンをしていて一日中ピアノの音が鳴り響くとか、階下に病人が住んでいて一日中お部屋の中で過ごしている等、どうしても音を止めなければならない環境の場合は中途半端な防音処理をしても、お金の無駄使いになってしまいます。
ここでポイントになるのは、防音室の広さ、天井の高さ、音の反射の具合を必ず事前にショールーム等に行って確かめてみる事です。
どうしても防音の事ばかりに目が行って、その中で音がどの様に聞こえるのかを忘れてしまい、結果的に防音室でピアノを弾きたくないなんてことになります。
また、ユニットの防音室を購入するのか部屋自体を防音にするのかで、費用も100万円台から1000万円台までと大きな開きが出てきます。

防音室を作るのであれば、現在はボックス イン ボックス工法と言う、お部屋の中で防音室自体を浮かせたような状態で作る工法が防音効果が高いです。
ただし、この時も家を建てる時点で防音室を作る事を前提に設計してもらう事が理想ですし、防音工事の経験の豊かな工務店に依頼する事をおすすめします。
4.ピアノ調律師がお勧めする防音対策製品5選
1-1サイレントユニット
価格もユニット代と取り付け費用含めてで約20万円~ですが、ピアノの年式、状態によって取り付け費用が変わります。
また、鍵盤数の少ないピアノや一部の小型ピアノには取り付け出来ない場合が有りますので、事前にお問い合わせ下さい。

1‐2ナイトーン
アップライトピアノには殆どの機種にマフラーペダル(3本有るペダルの中央のペダル)がついており
マフラーをONにすることでピアノの音量を下げる事が出来ます。
しかしマフラーを使うとピアノタッチが変わってしまったり、ダンパーペダル(一番右のペダル)を踏んで演奏した時に
いろんな音が混ざって、音が濁って聞こえたりします。
そんなマフラーの弱点を克服して、ピアノから発せられる音を十分の一位まで落とせる、ナイトーンと言う改良マフラーを取り付ける防音方法が有ります。
こちらの利点はタッチ感覚がほぼ変わらないで、小さな音でピアノ演奏を楽しめることです。
もちろんマフラーを外せばいつも通りのピアノの音に戻ります。
価格もアップライトピアノで20万円~、グランドピアノの場合で約30万円~となります。

2.ピアノパネル

価格はアップライトピアノで2万円~8万円、グランドピアノの場合で約12万円~20万円となります。

カワイのグランドピアノの場合、カワイ特注のピアノマスクと言う製品を後付けすることも可能です。
ピアノマスクはピアノ下部の遮音板を開閉出来るので、音を出しても大丈夫な時は開放して本来のピアノの音を出すことが出来ます。

3.防音インシュレーター、防音マット


4.吸音材、遮音材
アップライトピアノ用の吸音、遮音は4万円台から色々な製品が販売されています。
ただしこの方法の場合、お客様だけで判断するのは難しいと思いますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

5.まとめ
ピアノを演奏する人にとって、防音はエチケットであり、隣近所の方との人間関係を良好に保つための手段でもあります。
これまでお伝えしてきた防音の方法は以下の通りです。
1.ピアノ本体の音を小さくする、消す。
2.ピアノから発する音量、音圧を下げる。
3.ピアノから出る個体振動を抑える。
4.ピアノから出る空気振動を抑える。
5.部屋全体を防音する。
これらのどの方法を行うかは、ピアノを演奏する方が何を第一に求めるかによります。
ピアノの音の事で後で嫌な思いをしたり、近隣住人との人間関係で悩んだりすること無く、胸を張って生活していけるようにすることが大切なことでしょう。
ピアノは心を豊かにし、生活にうるおいを与えてくれるものですが、ちょっとしたいざこざからピアノを弾くことが怖くなってしまう、なんて事になるかも知れません。
そんな残念な事にならない為にも、日頃から近隣住民の方のコミュニケーションを大切にして、心置きなく好きなだけピアノを楽しめる環境作りを心掛けて頂けたらと思います。
私達もそんなピアノに触れて心豊かに生活出来るよう応援致しますので、お悩み事が有りましたら遠慮なくご相談下さい。
何かお困りの事やお聞きになりたいことが御座いましたら、
℡ 0120-045-845
またはbzq21747@gmail.comにメールで問い合わせてください。
ピアノ職人・VIRA JAPAN
(有)ラッキーパイン
〒243-0804 神奈川県厚木市関口466‐1