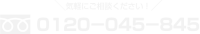1 .全体の状況を見て修理費用を見積ります
ヤマハU5と言うピアノは1967年頃に製造されたピアノです。
実は、12年前の2010年に当社に修理見積りを頂いていたのですが、
色々な事情から修理が先延ばしになっていました。
今回お客様から改めてご依頼を頂き、大変光栄で嬉しく思いました。
さて、製造から55年経過しているピアノはどんな状態でしょうか?
先ずは全体の状況を調べていきます。
この記事にご興味のある方は、こちらからメールかお電話でお問い合わせ下さい。
℡ 0120-045-845
またはbzq21747@gmail.comにメールで問い合わせてください。
ピアノ職人・VIRA JAPAN
(有)ラッキーパイン
〒243-0804 神奈川県厚木市関口466‐1
当初の見積もりから10年以上経過しているとピアノの状況も変化しますので、
保管先の倉庫に下見に伺って、状態を確認しました。
ずっとピアノの運送店の倉庫で保管されていたようで、
それほど傷みも進んでないように見えました。
加えて10年越しに、修理のご依頼頂けた事に感謝して
当時の見積もり内容で対応する事を決めました。
しかし、実際に各パーツをチェックすると、かなり傷みが出ていましたので、
作業内容をアレンジして、予算内に収まるようにしました。
2.いざ修理開始
年数の経過したピアノは全体的に部品の劣化が発生していて、
一部分を修理、調整すれば終わりとはなりません。
金属部のサビの発生、フェルトやクロスの摩耗や硬化、
各部品の寸法の狂い、木部の反りやねじれ、
接着剥がれやビスのゆるみなどなど
見るポイントは沢山有ります。
取りあえずは、鍵盤とアクションの修理、調整から入ります。
アクションはハンマーが戻らないスティックが沢山有り、
ブライドルテープも茶色く変色し朽ちていましたので、
スティック修理に合わせて全て交換します。
ブライドルテープの長さを均一に揃える為、簡易治具を作りました。
部品の寸法を揃えるのも大切な事です。
それをなるべく簡単に誤差を少なくする為に
こんな簡単な事でも作業効率が大きく上がります。
3.アクション修理
アクションの修理は音色、弾き心地に大きく影響しますので
部品の一つ一つを入念にチェックしながら進めて行きます。
ハンマーもシェービング(ピアノの弦をたたくハンマーの表面を削る作業)
をして音色の調整をしました。
また、ヤマハ特有のフレンジコード切れに関しては
この年代のピアノは大丈夫でした。
ダンパーの止音状況も問題有りませんでしたので、
これらの作業はパスして、その分を他の修理に回します。
4.本体修理
本体に目を移すと何故か養生テープが張ってありました。
お客様に確認したところ、保管先の運送店で
ピアノの裏の板が剝がれかかっているとの事で
裏の化粧板を固定する為に貼ったようです。
しかし、塗装面に粘着テープが貼ってあると
時間の経過と共に塗装面が傷んでしまうので、
剥がして、裏面の補修を行いました。
ピアノ背後の化粧板剥がれは何回かに分けて、接着しました。
本体は一度調律して弦のテンションを上げてから、弦とピンのサビ落としをします。
チューニングピンは真鍮ブラシとゴムチューブを使って、
ピンのサビを一つ一つ落として行くので、手間と時間がかかります。
弦はサンドラバーと真鍮ブラシ等を使って55年分のホコリとサビを落として行きます。
作業する自分も、何かサッパリした感覚になります。
次に鍵盤を外して見ると、中は虫食いの被害が有り
フロントパンチングは全交換する事にしました。
ピアノの内部はフェルトやクロス等、衣類の虫が好む素材が多く使われていますので
どうしても虫食いの被害が発生します。
日本の多湿の気候は虫にとっては好条件な環境で、
ピアノ内部に入り込むと一ヵ所から広がり増殖して、
ピアノの内部全体に被害を及ぼします。
特に使われなくなったピアノは、虫達にとっては恰好の繁殖場所となります。
フタを開ける事の無くなったピアノの中は、常に温暖で静かです。
食料となるフェルトやクロスも沢山あります。
虫にとってはまさに楽園です。
通常、虫は鍵盤下のパンチングや鍵盤のブッシング辺りから食べだして
そのうちアクション部品やマフラーフェルト、ハンマーフェルトまで
食べだしてしまいます。
こうならない為にも、定期的な調律や
ピアノの中に防虫剤を入れるなどの対策をお願いしたいです。
パンチング交換と共にバランスピン(鍵盤中央部の穴に差し込むピン)と
フロントピン(鍵盤の手前側の穴に差し込むピン)共々
サビが出ていましたので、サビ落としもします。
特にバランスピンは鍵盤の動きの中心点となる場所なので
このピンがサビたり汚れたりすると、鍵盤の動きの抵抗となります。
従って鍵盤のバランスホールと共に調整する事で鍵盤タッチが滑らかになります。
磨き込みは手作業で、赤いパンチングを一度取り外した状態で行います。
理由はピンの根元が一番鍵盤と接する場所で、
尚かつ一番サビが発生しやすい場所だからです。
ここが新品時の様な状態になっていれば
少なくとも鍵盤の動きはスムーズなはずです。
こうやってサビ落としや汚れを落として、
少しでも新品の時の状態に戻して行きます。
ケース内に溜まったホコリや弦や
ピンを磨いて出たサビ、ブラシのカス等は
その都度コンプレッサーと掃除機を使って綺麗に掃除します。
ここまでで本体のメンテナンスは70%位完了となります。
5.鍵盤調整
鍵盤は演奏者の想いを表現するための大変重要なパーツです。
実際に音を発するのは弦の振動とそれを増幅する響板ですが、
そのスタートとなるのがこの鍵盤です。
鍵盤は引っ掛かったり、ガタついたり、もたついたりすることなく
滑らかにストレス無く動く事が必要です。
そのためには各部品の状態が良好でなくてはなりません。
加えて鍵盤そのものの肌ざわりや感触もタッチに微妙に影響します。
従って、鍵盤の汚れを落としながら
各パーツの摩耗や不具合をチェックしていきます。
鍵盤も知らず知らずの間に汚れが付着します。
見た目にも汚れて古ぼけて来ます。
それを丁寧に落とし込んで行きます。
この鍵盤調整も88鍵全てをやると、結構体力を使うんです。
一つ一つバフで研磨するのですが、
特に中央部付近の白鍵は一番使われる所なので
爪のひっかき傷が沢山付きます。
これを綺麗に落とすのにはバフの前の下処理が重要となります。
ですから鍵盤1台分を調整するのに、半日から1日かかります。
鍵盤はキートップ(鍵盤の上面)だけではなく、
鍵盤の手前側の木口や鍵盤の両サイドの木場も
汚れて黒ずみます。
指で触るキートップのみ綺麗にすれば良いという考え方もありますが、
やはりやるのなら、全体が綺麗な方が良いですよね。
ですから白鍵も黒鍵も全部同じように綺麗にします。
全てやり終えると、見た目も触った時の感触も変わります。
鍵盤調整は外側を綺麗にするだけではなく、
鍵盤のブッシングやスロットル(鍵盤側の穴)もチェックします。
ブッシングが摩耗している場合は交換も必要ですし、
鍵盤を本体に戻した時に、バランスホールへの抵抗が大きい場合には
バフ研磨の後に穴コロシやブッシング調整作業も行います。
とにかく、鍵盤とアクションはタッチに直接影響しますので、
出来るだけ細部までメンテナンスをします。
6. 本体クリーニング
①カビの除去
本体をねかせて、底板を外して内部のチェックを行います。
すると、鍵盤が乗っている棚板の裏側にカビが発生していました。
棚板の裏側は殆ど見る事が無い場所なので、
知らないうちにカビが発生していたりします。
カビはピアノの内部だけでなく、多くの場所に発生しますので
定期的に点検、調整することが大事になります。
今回はピアノの内部全体を拭き取ってカビを除去しました。
②底板とペダル調整
湿気の多い所に長期間置いてあると
底板のビスが錆びついて途中で折れてしまいます。
ネジを外す時は錆びつき具合を指先で感じ取りながら慎重に外して行きます。
このピアノのビスは、サビは出ていましたが折れたのは1本だけでした。
しかしサビの発生が多いので、全て交換します。
次にペダルを外して磨き上げます。
工程は
1.薬剤を使ってのサビび落としの下処理
2.サビ落としの薬剤除去
3.下処理磨き(荒磨き込み)
4.バフ研磨
5.仕上げ処理
6.コーティング処理
の6工程となります。
ペダルを取り付けるパーツのクッションも古くなっていたので、
新品に交換しました。
細かな作業ですが、こんな作業の積み重ねで、ピアノ全体の弾き心地が違って来ます。
今日はペダルを底板に取り付けて作業完了としました。
本体の塗装面の仕上げに入りました。
パーツ毎にサビ落とし、汚れ落としを行って行きます。
今回のヤマハU5の場合は、半艶塗装の為、
サビ落としはマスキングテープで養生して
全て手作業で金属部分だけを磨き上げて行きます。
③塗装面調整
本体の汚れ落とし、塗装面の調整であれば、
洗剤を使った洗浄と洗浄後の仕上げ処理でOKなのですが、
鍵やエンブレム等の真鍮がはめ込まれた場所の処理は
そう簡単には行きません。
特に艶消しや半艶仕上げの塗装の場合は
金属部と一緒に磨きこむ事が出来ません。
何故なら磨いた部分だけ光沢が出てしまい
他の場所との光沢の違いが不釣り合いとなってしまうからです。
従ってマスキングテープを張って、
塗装面をなるべく傷つけないように、細かな作業が続きます。
鍵盤おさえはフェルトが途中欠損していましたので、
新しいフェルトに張り替えました。
フタの部分は一番目に付くところです。
ピアノの中でも鍵盤フタの表、裏とその近辺は最も目線に近く、
その為、小さなキズや汚れも目立ちます。
おまけに譜面台のヒンジやエンブレム、カギ等の金属が埋め込まれ
その金属がサビて見た目も汚くなってしまいます。
ですから、一番力を入れて作業をします。
先ずは鍵盤ブタと奥丸(フタの奥のパーツ)をジョイントしている
ロングヒンジ(真鍮製の丁番)を外して、パーツ毎に作業出来るようにします。
はずしたロングヒンジはペーパーやサンドラバーで下処理をして
バフ研磨、コーティング処理を行って行きます。
鍵穴、エンブレムはやはり金属部分のみを磨き上げる為にしっかりと養生をして
時間をかけて手作業でサビ落としを行って行きます。
黒の艶有りピアノでしたら、細かいペーパーでサビを落としてから
バフ研磨すれば済んでしまうのですが、半艶仕上げのピアノはそうはいきません。
とにかく、コツコツと時間をかけて手作業で進めて行きます。
譜面台のヒンジは取り外して磨き上げます。
かなりのサビが出ていましたので、下処理のサビ落としに時間がかかりました。
作業工程はロングヒンジと同じく、ペーパーやサンドラバーで下処理してから
バフ研磨をして、最後にコーティング処理をします。
こうやって一つ一つのパーツを仕上げて行きます。
本体の作業と各パーツの調整も終わり、
本体に底板を取り付け、鍵盤とアクションも組み付けました。
やっと元のピアノの形に戻りました。
音出ししてみた所、スムーズで滑らかなタッチでしたが、
これから暫くシーズニングで各パーツを慣らしていきます。
お預かりした時の状態から比べて、
鍵盤はとてもスムーズに動くようになりました。
また、外装もサビ落としや汚れ落としを終えて
化粧直ししたような気持ちです。
本体の金属部にはサビ防止のフィルムを貼り付けました。
後は出荷調律と最終チェックをしてお戻しの手配に入ります。
この記事にご興味のある方は、こちらからメールかお電話でお問い合わせ下さい。℡ 0120-045-845
またはbzq21747@gmail.comにメールで問い合わせてください。
ピアノ職人・VIRA JAPAN
(有)ラッキーパイン
〒243-0804 神奈川県厚木市関口466‐1